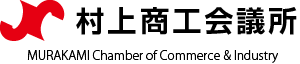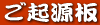
村上商工会議所
平成十九年・長谷川勲氏執筆
地域住民のコミニュティ復活や街中の賑わい作りのきっかけとして、住民の人たちが自分の住む町や他の町内の町名由来等を知るために、また観光客への説明用として岩船スギを使った町名の由来を記した木製看板です。
平成19年度の村上商工会議所事業で企画、製作を致しました。
村上大祭のおしゃぎりがある19町内の看板を設置しております。


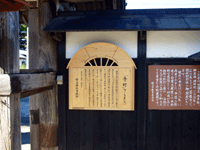
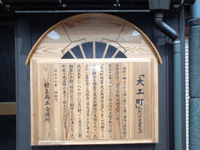

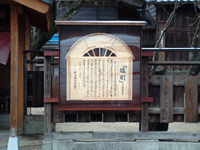
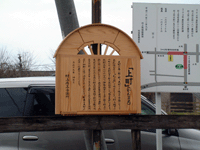




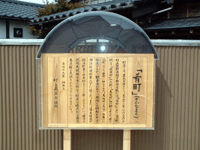


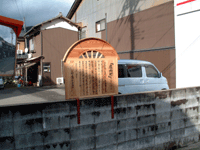
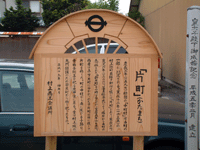


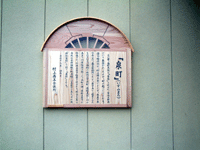
(01) 久保多町(くぼたまち)
堀氏時代の城下絵図に「窪田町」と見え、町並み北側には馬場(おいまわし)が描かれている。寛永九年(一六三二)、直竒公の兜守り馬頭観世音菩薩を本尊として観音堂が建てられたが、後に塩町に移された。正徳二年(一七一二)の竈数は一二四。
享保六年(一七二一)の大火を経て、従前の「久保田町」を「久保多町」と改め、明和五年(一七六八)、観音堂跡地に遠州から秋葉神社を 勧請した。今、参道に立つ大欅は、馬場先観音堂が建てられていた当時の樹である。
(02) 大町(おおまち)
村上城の大手門(追手門)前の町。上町との境は安良町へのT字路となり、高札場があって「札の辻」と呼ばれた。
寛永十年(一六三三)、元羽黒にあった羽黒神社の現地への遷宮の折、当町が車に載せた太鼓を打って町を練り歩いたのが、村上大祭の初め とされる。同十二年(一六三五)の村上惣町並銘々軒付之帳には家数は三七軒とあり、寛文五年(一六六五)の文書には当町に十一軒の造り酒屋が見える。大町の由来は城下の中心的な繁華な町の意を込めたもの。
(03) 寺町(てらまち)
堀氏が城下町拡張の際、戦略上ここに寺を集めた。寛永十二年(一六三五)の村上惣町並銘々軒付之帳には、寺町二七軒、本塩町二〇軒とあり、寺は常念寺、経王寺など。願常寺は本塩町に見える。本塩町はこの地の塩町がすでに去っていることを意味する。
常念寺は泰叟寺を称した元禄二年(一六八九)、奥の細道の芭蕉が訪れた寺で、現浄念寺。土蔵造りの本堂は国重文で、享保五年(一七二〇)没の藩主間部詮房の御霊屋もある。町名は寺の多いことによる。
(04) 大工町(だいくまち)
寺町の中ほどから南へ延びる通り。南端は安良町と十字路をなし「茶ノ子町(現細工町)」に続く。寛永十二年(一六三五)の村上惣町並銘々軒付之帳には「大工町桶屋・大工無諸役之家」とあり一九軒のうち一五軒ある桶屋と大工は諸役が免除されていた。
ほかに善行寺と光西寺(現光済寺)の二か寺あった。元治元年(一八六四)には三八軒、うち大工は一八軒、桶屋一〇軒。明治になり料亭などが多くなった。町名は大工職の集まり住んだことによる。
(05) 小町(こまち)
大町の北に続き、中程でクランク状に折れて小町坂を下り、庄内町に接する。
小町坂の部分を古くは下小町と呼んだ。寛永十二年(一六三五)の村上惣町並銘々軒付之帳によれば、家数は「小町」三四、「下小町」一三とあり、元禄二年(一六八九)、芭蕉が奥の細道の途次、弟子の曾良と二泊した「宿久左衛門」があった。旅籠屋の多い町で、安政二年(一八五五)、幕末の志士清川八郎も投宿し、城下の見聞を書き遺している。
町名は大町に並ぶ古い町立てから。
(06) 塩町(しおまち)
元和(一六一五~二四)の頃の越後村上城図に小町と下小町の間に「シヲ町」の名が見える。このシヲ町とのかかわりは明確でないが、寛永十二年(一六三五)の村上惣町並銘々軒付之帳には「本塩町」二〇軒が載っており、位置は大町と寺町の間である。村上城主歴代譜によれば、この本塩町が藩主松平大和守により今の塩町に移されたものといい、町名は小町が持つ塩の占専売権を受け地浜塩を扱ったことに由来するという。宝永二年(一七〇五)の家数は八三軒。
(07) 上町(かんまち)
大町の南に続く町。大町との境は丁字路になって高札場があり「札の辻」と呼ばれていた。村上城下の一町だが、元和初年の村上城絵図には「風呂屋町」とある。
元和五年(一六一九)、伊勢地方から茶の種を村上に持ち帰って蒔いたという徳光屋覚左衛門は当町の人。寛永十二年(一六三五)の村上惣町並銘々軒付之帳では、家三六軒。
寛文五年(一六六五)当町には徳光屋覚左衛門ほか四軒の造り酒屋があったという。
町名は大町の上手に位置することによる。
(08) 細工町(さいくまち)
もとは村上氏の時代に上町の西側につくられた鍛冶屋町。加賀の小松から本蓮寺(本悟寺)を遷すにあたり、これを現在の鍛冶町に移したといい、寛永十二年(一六三五)の村上惣町並銘々軒付之帳には「本加治町」と見え、家数三四。飯野通り沿いには別に「六軒町」があり家七軒。町中ほどの十字路から安良町への通りは「茶ノ子町」と呼ばれ、宝永二年(一七〇五)の「寺社旧例記」には家数五軒。
町名は本蓮寺の旧地小松の細工町にちなむという。
(09) 安良町(あらまち)
大町の辻の札から西に、小国町までの町。寛永十二年(一六三五)の村上惣町並銘々軒付之帳には「あら町」「新町」とあり、家四一軒。なかに茶師庄次郎の名が見える。
茶師は茶商である。地名は大町、小町の後に新しくできた町の意で「荒町」とも書いたが、宝永二年(一七〇五)には、「安良町」とある。
明和六年(一七六九)の軒付帳では家数七八、なかに磯部順軒の寺子屋が見える。嘉永二年(一八四九)の家数は八〇軒。城下の大年寄が詰める町会所があった。
(10) 小国町(おぐにまち)
慶長年間に安良町に次いで出来た町という。寛永十二年(一六三五)の村上惣町並銘々軒付之帳には「小国町」と見え、家数六〇軒。なかに十人組頭が四人、鉄砲衆、鷹師衆が見える。これらの人を御組と呼び、後代、与力や同心とも称した。後に町立てされた鍛冶町との境には木戸があったという。塩町地内に祀る稲荷社は「同心稲荷」とも言い、現在まで小国町で維持している。天明二年(一七八二)の町軒付帳では、商家二〇軒、酒造屋二軒などが見える。
(11) 鍛冶町(かじまち)
当町の起こりは上町から西へ入る通りにあった鍛冶職衆六軒であったといい、「六軒鍛冶」の名が今も残る。この鍛冶衆が元和五年(一六一九)城主堀直竒によって、小国町と肴町の間の空き地に移されたものという。寛永十二年(一六三五)の村上惣町並銘々軒付之帳には「新鍛冶町」と見え、家数一七軒。移転前の町は同軒付之帳に「本加治町」と見える。宝永元年(一七〇四)の家数二一。明治以前は和釘の製造が盛んで、その後は打刃物などを生産してきた。
(12) 肴町(さかなまち)
町立ては、慶長年間という。寛永十二年(一六三五)の村上惣町並銘々軒付之帳には「肴町」とあり、四二軒。続いて「長岡町」一二軒、「馬喰町」四一軒とあるが、後の二町はのち肴町に併わされた。馬喰町は馬喰(伯楽)に由来するが、観音寺があり、西端には桝形があって瀬波街道松原八丁に通じた。また、藩主堀氏が鍛冶町裏の中貝村をここに移したともいい、鎮守の河内大明神は今に残る。町名は堀氏から魚の専売権を免許されたことによるという。
(13) 長井町(ながいまち)
上町から南へ延びる町並み。南端は羽黒町との間の桝形で、また上町との境の道は東方飯野門に通じる。近世初めは「田町」と称し、侍屋敷であったという。
城主堀丹後守直竒はこの侍屋敷を飯野に移して町屋とし、その後「長井町」と改められた。寛永十二年(一六三五)の村上惣町並銘々軒付之帳には、家数四二、竈数五三とある。
寛文五年(一六六五)の当町には、加賀屋、越前屋、小松屋などの造り酒屋があった。嘉永二年(一八四九)には家数七三軒となる。
(14) 羽黒町(はぐろまち)
家並みはほぼ東西に延び両端に桝形が設けられていた。この辺りは慶長二年(一五九七)の瀬波郡絵図には「しり引村」と見えるが、やがて「新田村」となる。寛永十年(一六三三)、臥牛山の羽黒神社を当町へ遷座する際、羽黒口周辺の「坂ノ下」集落も移し、新田村と併わせた。 二年後の村上惣町並銘々軒付之帳には「羽黒町」と見え、家数三九。堀氏時代に塩の占売権を得たが、その後、地浜塩の塩町に対し旅塩を商う。町名は西奈弥羽黒神社の鎮座による。
(15) 庄内町(しょうないまち)
河岸段丘下を東西に延びる町。南側家並み裏に村上城の大きな堀があり、その東方を「広見」と呼んだ。町の東の端を北に折れると正面に桝形があり、久保多町に通じた。
榊原氏時代(一六六七~一七〇四)の城下絵図には、現在の専念寺小路に「鷹匠町」と見え、町の西部で北に入る小路の東に「篭屋」と記されている。寛永十二年(一六三五)の村上惣町並銘々軒付之帳には家数六九、長柄衆一軒、鉄炮衆三軒、などが見える。嘉永二年(一八四九)の家数一二〇軒。
(16) 片町(かたまち)
慶長二年(一五九七)絵図の「中町村」は当町の一部に比定される。寛永十二年(一六三五)の村上惣町並銘々軒付之帳には「片町」とあり、家数六一。寛文六年(一六六六)、藩主松平氏により、堀片から当町の先へ移された「新片町」も一時は含んだが、宝暦元年(一七五一)、両者は上・下片町に別れ、のち下片町は旧に復して片町を称した。町の中程から南に延びる小路は、青面金剛王を祀る庚申堂に至る。堂は村上城の鬼門鎮護のため荒町から移し祀ったもの。
(17) 上片町(かみかたまち)
当町はかつて現在の堀片にあった町という。寛永十二年(一六三五)の村上惣町並銘々軒付之帳に「片町」とあり、家数六一。城主松平大和守は、侍屋敷拡張のため寛文五年(一六六五)、この町を山辺里河畔へ移転し「新片町」と呼んだという。その後、元禄十三年(一七〇〇)に、「上片町」を称し片町と別れた。肴町から続く城下の東端で、山辺里橋の橋本に近い延命地蔵尊は、口碑によれば元和四年(一六一八)、城主堀氏が旧茅倉より移し祀ったものという。
(18) 加賀町(かがまち)
庄内町東北端にあった桝形から橋を経て西に延びる町。西端は塩町に接する。寛永十二年(一六三五)の村上惣町並銘々軒付之帳には見えない。村上雑記に「大和守様御在城十九年之内、塩町、加賀町、新片町出来」とあることから、慶安二年(一六四九)から寛文七年(一六六七)までの間に町立てされたことが分かる。寺社旧例記によれば、宝永二年(一七〇五)の家数二九、文政年間(一八一八~三〇)の当町絵図家業附では、三一軒半・竈数六九。木挽き職、大工が多かった。
(19) 泉町(いずみまち)
その昔、当町界隈は「萱場」と呼ばれ、萱場七軒衆という集団があったのが、町の起こりとされる。鎮守稲荷社は、村上郷土史によれば、永正十年(一五一三)、春日右衛門によって、桑中島から遷宮されたものという。当時の社地は下渡村、通称見出しの川の土手で川原稲荷を称した。元和の頃、通称土居下に移遷され、以後土居下稲荷と呼ばれる。明治十六年の寺院仏堂明細帳の町名欄には土居下と見え、その後「新加賀町」を経て「泉町」となる。